Studioはデザイン性が高く、操作も直感的なノーコードツールとして人気を集めています。しかし、HTML/CSSの基礎がある方が実際に使い始めると、「思ったより自由が利かない」と感じる場面も少なくありません。多機能さを求める開発志向の方ほど、気づきにくい制約に戸惑うことがあります。
本記事では、Studioを使い始めたばかりのコーダー・デザイナー向けに、システム面・デザイン面・パフォーマンス面などの制限をわかりやすく整理し、ツール選定の参考となる情報を提供します。なお、これはStudioを否定するものではなく、Studioを実際に活用し好んでいる立場から、より効果的に使いこなすための改善点としてまとめたものです。
※本記事の内容は2025年6月27日時点のStudioの仕様に基づいています。2025年6月には動画アップロード機能や動画通知機能の追加などのアップデートが行われています。今後のアップデートで改善される可能性がございますので、何卒ご理解ください。
目次
システム開発・機能面での制限:バックエンド処理の壁

StudioはWebサイト制作には便利ですが、ログイン機能やEC構築など、Webアプリケーション的な機能を必要とするプロジェクトには不向きです。業務での機能要件を正しく洗い出してから、Studioが適しているかを判断することが重要です。
会員登録・ログイン機能は非対応
HTML/CSSでフォームを作成した経験があるあなたなら、「ログインフォームを作って、PHPやJavaScriptでユーザー認証を…」と考えるかもしれません。しかし、Studioでは会員登録機能やログイン機能を実装することができません。
| 機能 | 従来のHTML/CSS | Studio |
|---|---|---|
| 会員登録・ログイン | PHP/JS等で実装可能 | ❌ 実装不可 |
| ECサイト機能 | 決済API等で完全実装可能 | △ 外部ツール必要 |
| データベース連携 | 自由に設計・実装可能 | ❌ 対応不可 |
| カスタムJavaScript | 自由に記述可能 | ❌ 直接編集不可 |
| CSS疑似要素 | ::before, ::after使用可能 | ❌ 使用不可 |
| フレキシブルサイズ | clamp(), calc()使用可能 | ❌ 固定/可変のみ |
クライアントから「会員登録機能付きのサイトを」と依頼された場合は、事前に制約を説明し、別のソリューションを提案する必要があります。
ECサイト構築には外部ツールが必要
Studio単体では商品管理やカート・決済などのEC機能は実現できません。フル機能のネットショップを目指すなら、ShopifyやBASEなどの専用サービスを選択する方が安全です。
- 📕部分的に可能なこと:
- ・Stripeの埋め込みによるECサイト風ページ作成
- ・ShopifyのAPIを使った商品データ表示
「ECサイト風のページ」と「本格的なECサイト」は全く異なります。見た目は商品カタログのようなサイトが作れても、実際の販売機能は別途システムが必要であることを明確に伝えましょう。
複雑なシステム連携には対応していない
Studioは、あくまで「Webサイト制作ツール」です。業務用Webアプリやデータベース連携など、複雑なバックエンドを要する開発には不向きです。API連携やユーザーデータベースの構築を想定しているなら、Studioでは不十分となります。
デザイン・技術面での制限

Studioはノーコードでありながら高品質なデザインが可能ですが、HTML/CSSの細かな調整や動きの追加など、コーディング経験者が期待する柔軟性には限界があります。
pタグ内でのspan使用不可
HTML構造を理解している方には直感的に理解できる制限です。通常のHTMLでは、pタグ内にspanタグを挿入して特定の単語の色やフォントを変更することが可能ですが、Studioではpタグ内にspanタグを直接挿入することができません。ただし、リッチテキストを使用することで一部の文字色変更などは可能ですが、一定の制限があります。
👉代替案:リッチテキストで一部文字色を変える方法。
テキストの改行位置制御不可
画面サイズごとにテキストの改行位置を細かく調整する機能がありません。そのため、デザインの細部にこだわりたい場合、不便に感じることがあります。スマホのみ表示して改行したりする事はできますが、文字数が多かったり、画面によって改行が多数必要な場合、かなりの手間と時間を要します。文字の装飾や見た目にこだわる人にとっては、痒いところに手が届かないと感じる可能性があります。
👉代替案:画面毎の表示・非表示での改行
レスポンシブ・編集環境の制限

Studioはスマホでも表示を確認できますが、編集作業はPC環境のみ。レスポンシブ対応もブレイクポイントに依存するため、柔軟なマルチデバイス対応には注意が必要です。
柔軟なレスポンシブ調整が難しい
CSSのclamp()のような柔軟なサイズ指定や、vwによるマージン調整が行えず、レスポンシブ設計にこだわる人にとっては物足りなく感じるでしょう。 特に中間サイズのデバイス(小さなタブレット、大きなスマートフォン等)での表示崩れが起きやすくなります。
ブレイクポイント数に制限あり
| ブレイクポイント | サイズ | 設定 |
|---|---|---|
| 基準 | 1280px | デフォルト |
| スモール | 1140px | 追加可能 |
| タブレット | 840px | デフォルト |
| モバイル | 540px | デフォルト |
| ミニ | 320px | 追加可能 |
Studioではブレイクポイントは上記の通り最大5つまであります。独自に追加することはできず、細かいデバイス対応に限界があります。細やかな画面最適化をしたい場合には制限と感じるかもしれません。どうしても、調整が必要な場合、iframeのブロックを使用してCSSを追加する事もできますが一定の制約があります。
👉代替案:iframeのブロックを使用しCSSで細かいレスポンシブを設定する方法
画面幅が650pxから800pxの範囲の時のみ、thanksページのコメントボックス(idがbox)を非表示にしたい場合、iframeのブロックを利用し、CSSで制御する方法を使用します。
<style>
@media screen and (min-width: 650px) and (max-width: 800px) {
#box {
display: none;
}
}
</style>フォーム・CMS・コンテンツ面の制限
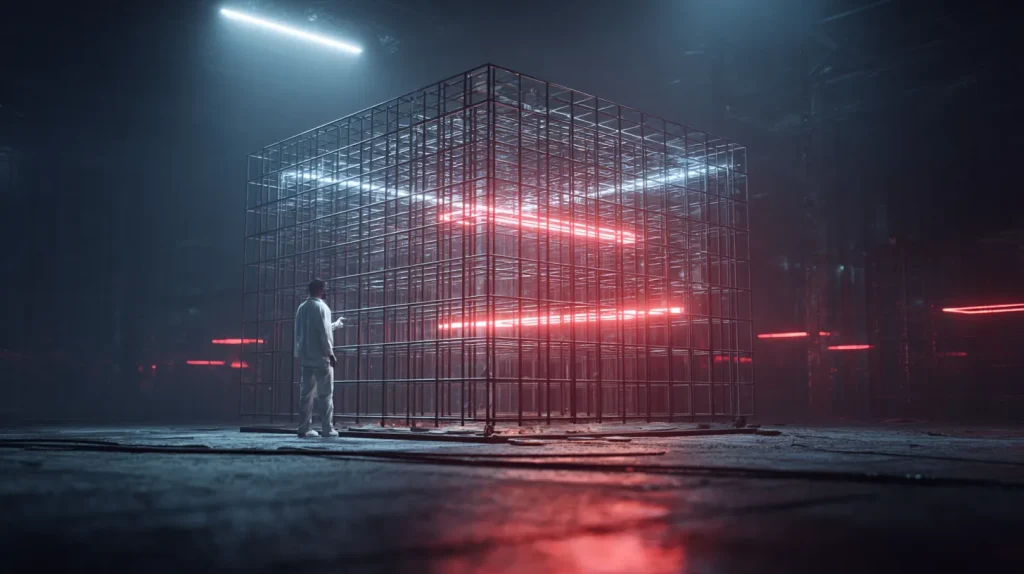
Studioは簡易的なフォーム機能を備えていますが、実務で使うには物足りない点も多く、コンテンツ管理や投稿システムもシンプルに留まっています。ビジネス用途では、フォームの要件とセキュリティも要チェックです。
問い合わせフォームがシンプルすぎる
| 項目 | 詳細 | 従来の開発との比較 |
|---|---|---|
| 自動返信メール | ❌ 対応なし | ✅ PHP/JSで実装可能 |
| フリーメール制限 | ❌ 制限不可 | ✅ バリデーション実装可能 |
| 高度なバリデーション | ❌ 基本機能のみ | ✅ カスタム実装可能 |
| 送信データの加工 | ❌ 不可 | ✅ サーバーサイドで自由に処理 |
Studioのフォーム機能は自動返信がなく、Gmailなどのフリーメール制限も不可。企業サイトや顧客対応を想定している場合は、別のフォームサービスと組み合わせる必要があります。
動的なブログ・CMS管理には不向き
数十〜数百記事を扱うブログ運用には適していません。更新性が高いメディア系サイトを作りたい場合はWordPressなどのCMSが無難です。
- 具体的な制限:
- ・ページネーション機能がない(記事が多い場合は「もっと見る」ボタンなどで対応)
- ・記事の関連記事を自動表示する機能がない
- ・カテゴリやタグによる記事の絞り込み機能が限定的
- ・プランによってCMSモデル数やアイテム数に上限がある(無料プランでは1,000アイテムまで)
閲覧可能回答数の上限
| プラン | 閲覧可能回答数 |
|---|---|
| Free・Mini | 100件 |
| Personal | 1,000件 |
| Business・Business Plus | 10,000件 |
長期運用での課題は、データが蓄積されていくと、過去の問い合わせ内容が参照できなくなります。顧客管理の観点では大きな制約です。
ページ・サイト規模の制限:大規模案件への対応不可
✨プラン別ページ数上限
| プラン | ページ数上限 |
|---|---|
| Free | 50ページ |
| Mini | 2ページ |
| Personal | 150ページ |
| Business | 300ページ |
| Business Plus | 300ページ |
| Enterprise | カスタム |
企業サイトで商品ページが多数必要な場合や、ブログ記事を大量に掲載する場合は、上限に達する可能性があります。
SEO・パフォーマンス面の制限
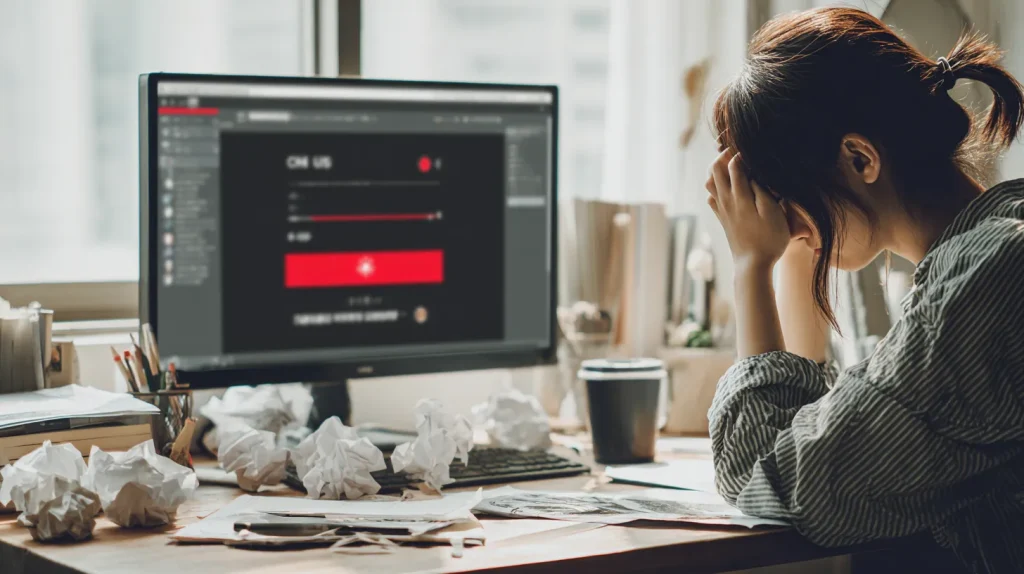
Google検索を意識したSEO対策や高速表示を目指す場合、Studioの標準機能では対応しきれない場面があります。特にWebマーケティング目的のサイトには相性の見極めが必要です。
細かなSEO最適化が難しい
| SEO項目 | 従来のCMS/コーディング | Studio |
|---|---|---|
| 構造化データ(JSON-LD) | ✅ 自由に記述可能 | ❌ 制限あり |
| カスタムメタタグ | ✅ 完全制御可能 | △ 基本項目のみ |
| robots.txt | ✅ 詳細設定可能 | △ 基本設定のみ |
| サイトマップ制御 | ✅ 完全制御可能 | △ 自動生成のみ |
| 内部リンク最適化 | ✅ 細かな調整可能 | △ 制限あり |
| ページ表示速度最適化 | ✅ 手動最適化可能 | ❌ システム依存 |
ページごとのmeta設定は可能ですが、構造化データやカスタムスクリプトの挿入、内部リンクの最適化といった細部調整には限界があります。SEO施策を細かく実施したい場合には不利になる可能性があります。
無料プランではインデックス申請が制限される
無料プランでは、Google Search Consoleを使ったインデックス登録のリクエストが制限されています。検索結果に確実に表示させたいサイトは、有料プランへの移行を検討する必要があります。ただし、外部サイトからのリンクなどによって自然にインデックスされる可能性もあります。
ページ表示速度の改善が難しい
PageSpeed Insightsなどのスコアが低いと感じても、構造自体に手を加えられないため、大幅な改善は難しいのが現状です。LCPやCLSなどのコアウェブバイタルに関するチューニングが困難です。
- 💡表示速度を改善するためのヒント:
- ・ボックス数を削減する
- ・画像の最適化を行う
- ・不要なアニメーションを減らす
- ・フォント設定を最適化する
運用・保守に関する制限

運用後の保守作業やトラブル対応を考えたときに、Studioはバックアップやテスト環境などの機能が不足している点に注意が必要です。規模が大きくなるほど運用リスクが増す傾向にあります。
バージョン管理機能はあるが活用が必要
Studioにはバージョン管理機能があり、最大360日前の状態に復元することが可能です。誤って上書き・削除した場合に備えて、定期的に手動でバージョンを保存しておくことをおすすめします。重要な更新の前には必ずバージョンを保存し、名前を付けて管理しましょう。
ページネーションやスクロールバーの調整不可
ブログや記事一覧でよく使われるページネーションが設定できません。また、縦長コンテンツのスクロールバー自体は表示できますが、その見た目や挙動を細かくカスタマイズすることはできません。UXを重視したサイト設計では気になるポイントです。
HTML/CSS経験者向け:Studioとの上手な付き合い方

案件の見極め基準
| 案件タイプ | Studio適用度 | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| コーポレートサイト | ✅ 適している | ページ数・機能が適度 |
| ランディングページ(LP) | ✅ 適している | シンプルな構成 |
| 小規模店舗サイト | ✅ 適している | 基本情報の掲載メイン |
| ポートフォリオサイト | ✅ 適している | デザイン重視・機能シンプル |
| 会員制サイト | ❌ 不適切 | ログイン機能が実装不可 |
| ECサイト | △ 制約あり | 外部ツール必須 |
| 大規模サイト(100P超) | ❌ 不適切 | ページ数上限・管理の複雑さ |
| 業務システム連携 | ❌ 不適切 | API連携・データ処理の制約 |
ハイブリッド戦略: Studio で素早くプロトタイプを作成し、制約が明確になった時点で従来の手法に切り替える使い方も効果的です。
クライアントへの説明術
「ノーコードツールは便利ですが、従来の開発と比べて制約があります」という前置きから始めましょう。
- 具体的な説明例:
- ・「会員登録機能は外部サービスとの連携が必要になります」
- ・「表示速度の最適化には限界があります」
- ・「デザインの細かな調整に制約があります」
制約を説明するだけでなく、「この部分はStudioで、この機能は別途開発で」といった解決策もセットで提案しましょう。
スキル戦略の考え方
ノーコードツールとコーディングスキルは対立するものではありません。HTML/CSS の知識があるからこそ、ツールの限界を正確に判断し、適切な提案ができるのです。
今後のスキル戦略:
- 効率化ツールとしてのノーコード活用
- 制約を理解した上での適切な案件選択
- ハイブリッド開発手法の習得
- クライアント提案力の向上
まとめ:Studioは「用途」と「目的」を見極めて使うべき
Studioは、デザイン性と手軽さを兼ね備えた優秀なノーコードツールです。特に小規模サイトやポートフォリオ、ランディングページ制作には最適でしょう。
しかし、HTML/CSS経験者が求める高度な制御やカスタマイズを実現しようとすると、多くの壁にぶつかります。構築の自由度や拡張性を求めるなら、早い段階でStudio以外の選択肢も検討しましょう。
目的に合ったツール選定を行い、Studioの強みを最大限に活かしましょう。ノーコードの限界を理解しておくことが、賢いWeb制作への第一歩です。Studioの魅力を正しく活かすためにも、その制限や特性を冷静に把握しておくことが大切です。

